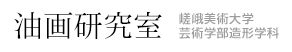京都嵯峨芸術大学・油画分野オフィシャルサイト|TOP|

宇野 和幸 uno kazuyuki
- 「気配としての実在」を具現化すること、「ズレが産み出す実感」の違和感を炙り出すこと
12 Visual Points 展に寄せて
<と> をめぐる12の考察
ここ金沢の地に12人のアーティストが集結し、「12 Visual Points 〜明日への視線〜」という展覧会を開催する。
2007年1月に開催された「6 Visual Points 〜明日への視線〜」の第2回展でもあるこの展覧会は、共通したテーマのもとに制作された作品が展示されるわけでも、それぞれが取り組む芸術の方向性におおいなる一致をみているわけでもない。むしろこの展覧会に関わる人達は、そういったテーマがいま必要なのだろうかとすら思っている。
アートシーンの(分かりやすさはともかくとして)面白さは、いろいろなアーティストの様々な視線からの思考や発言が、互いに絡み合い影響しあう中で、あるいはすれ違うごとに、直接的に間接的に触発されながらエスカレートし、サイクロンのような動きが加速して別次元の視点や思考が生まれていく、そことのダイナミックな関係性にあるといってもいい。
だからこそ、個展の集合でもなくコラボレーションワークとも違うこの展覧会において、作品と場と表現することへの意志が、それらの相関的なエネルギーが、新たな関係性が生まれる実体のある視点が立ち現れ、その先を見つめる「明日への視線」となり得る。
2つの作品、2人のアーティストがそこにいれば、ひとつの<と>が発生する。
しかしその<と>は単純な並列を示す「と」であるばかりではない。その意味合いは対比であったり、選択であったり、原因と結果の整合性であったりと、私たちの暮らす現実の社会同様に多種多様で一筋縄ではいかない関係性が含まれている。
問題は「関係性」なのだ。
アイデンティティを前提としないで関係性を問うのは無意味はではあるが、関係を遮断したアイデンティティもあり得ない。アーティストはその活動において自身の表現の中に関係性を、いわば<と>の問題を考え続けていかなくてはならないのだ。
それぞれのアーティスト達とその作品と金沢21世紀美術館とギャラリ−点と。
それらをつなぐ<と>の文字にはいろいろな意味が読み取れるだろう。英語で表すとしたら「and」なのか「with」なのか「join」なのか、あるいは「or」「to」「as」か、「on」「in」「into」?、ひょっとしたら「if」「when」「whenever」かもしれない。
それぞれの作品や作家のコンセプトが、他の作品や鑑賞者と、いま、この場所でかかわり合うことが重要なリアリティと意味を持つ。
この展覧会に向けての12人のアーティストの「作品」。それは<と>をめぐる12の考察として立ち上がる。
(2010年12月に金沢21世紀美術館、ギャラリー点で開催される「12 Visual Points -明日への視線-」展カタログ原稿より)
10/08/27
ここ金沢の地に12人のアーティストが集結し、「12 Visual Points 〜明日への視線〜」という展覧会を開催する。
2007年1月に開催された「6 Visual Points 〜明日への視線〜」の第2回展でもあるこの展覧会は、共通したテーマのもとに制作された作品が展示されるわけでも、それぞれが取り組む芸術の方向性におおいなる一致をみているわけでもない。むしろこの展覧会に関わる人達は、そういったテーマがいま必要なのだろうかとすら思っている。
アートシーンの(分かりやすさはともかくとして)面白さは、いろいろなアーティストの様々な視線からの思考や発言が、互いに絡み合い影響しあう中で、あるいはすれ違うごとに、直接的に間接的に触発されながらエスカレートし、サイクロンのような動きが加速して別次元の視点や思考が生まれていく、そことのダイナミックな関係性にあるといってもいい。
だからこそ、個展の集合でもなくコラボレーションワークとも違うこの展覧会において、作品と場と表現することへの意志が、それらの相関的なエネルギーが、新たな関係性が生まれる実体のある視点が立ち現れ、その先を見つめる「明日への視線」となり得る。
2つの作品、2人のアーティストがそこにいれば、ひとつの<と>が発生する。
しかしその<と>は単純な並列を示す「と」であるばかりではない。その意味合いは対比であったり、選択であったり、原因と結果の整合性であったりと、私たちの暮らす現実の社会同様に多種多様で一筋縄ではいかない関係性が含まれている。
問題は「関係性」なのだ。
アイデンティティを前提としないで関係性を問うのは無意味はではあるが、関係を遮断したアイデンティティもあり得ない。アーティストはその活動において自身の表現の中に関係性を、いわば<と>の問題を考え続けていかなくてはならないのだ。
それぞれのアーティスト達とその作品と金沢21世紀美術館とギャラリ−点と。
それらをつなぐ<と>の文字にはいろいろな意味が読み取れるだろう。英語で表すとしたら「and」なのか「with」なのか「join」なのか、あるいは「or」「to」「as」か、「on」「in」「into」?、ひょっとしたら「if」「when」「whenever」かもしれない。
それぞれの作品や作家のコンセプトが、他の作品や鑑賞者と、いま、この場所でかかわり合うことが重要なリアリティと意味を持つ。
この展覧会に向けての12人のアーティストの「作品」。それは<と>をめぐる12の考察として立ち上がる。
(2010年12月に金沢21世紀美術館、ギャラリー点で開催される「12 Visual Points -明日への視線-」展カタログ原稿より)
10/08/27
私の空間
くつろげる場所ではない。ホッとするわけでも癒されたりするわけでもない。別に自分のテリトリーというわけでもない。けれどもどうしても惹きつけられてしまう、「私の空間」と呼びたいところがある。
解体途中の建造物、特に廃工場の中だ。
少し前に廃墟ブームというものがあった。
そこでは、廃墟も廃屋もごっちゃにして、ある種のノスタルジーや、怖いもの見たさの肝だめし的覗き見感、過去の遺物を発掘するかのような探検家気分といったようなもので語られることがほとんどだったように思う。
そういった意味での廃墟・廃屋への興味というのは、私にはまったくない。
余談だが、廃墟と廃屋とは似て非なるものだと私は思っている。
建造物の大小に関係なく、ただ手付かずで放って置かれただけのものは、単に使われていない建物・廃屋であるけれども、そこでの生活感や人間のかかわりの痕跡がオブジェ的なモノへと昇華されて、さらに環境や自然とのコラボレーションが絶妙に成り立っているものが廃墟だ。雑草や油と埃のかたまりや得体の知れない薬品やシミで彩られている、モニュメンタルな建造物が、廃墟だ。

廃工場、特にその解体途中現場がいいのは、もともと生活の場として設置された空間ではないので、生活としての営みの痕跡がほとんどないことだ。ひたすら武骨に機能的に、しかも人間的ではない無駄にあふれている。目的と用途に特化された構造が、感情の入り込む隙間のない絶対的な荘厳さを纏っている。
それらがその目的である機能を停止させられ、再利用できる機材や部品は取り外されて、素の姿があらわになる。用途を剥ぎ取られた油まみれの鉄骨ががっしりとそそり立っている。むき出しの骨組みが縦横無尽にひたすら合理的に張り巡らされ、意味のなくなった仕切りと役割を見失った金属の塊が、建物や道具としてではなくその存在を静かに誇示している。
それが解体途中ともなると、これから壊されていくのかそれとも組み上げられていくのか、どちらにも向かっていけそうにさえ感じさせられる。きっと古びたまま新たに建ちあがっていく為にひっそりとエネルギーを蓄えているに違いない、そう思わせる独特の生命感を孕んだ質感がある。
ほこりをかぶっているのがいい。油汚れがこびりついているのがいい。途中な感じなのがいい。植物に侵蝕されているのがいい。なにかが変色しているのがいい。錆がいい。永久に乾かないかのような水溜りがあるのがいい。何かが現れ出そうな奥行きの深い薄暗さがいい。音がないのがいい。
そこは決して心安らぐ場所ではない。異臭が漂い、きっと何か体に悪いものを吸い込んでいるに違いない。怪我でもして動けなくなって、ここから出られなくなっても、誰も気付かないかもしれない。もしかしたらここで遭難・・・!?。そんなこともなぜか、いい。
湧き立つ不安と予感と開放感と衝動とにもてあそばれながら、私はそこに立つ。
イタリアの田舎町の教会で初めてステンドグラスを見た、その見事なステンドグラス越しの光に抱かれて立った時の、あの感覚にどこか似ている。
一時期、自分の作品について、廃墟がモチーフだと言っていたことがある。
原初的な力強い構造体を画面の中に存在させたいと格闘していた当時のことだ。鉄錆を主要画材とし使いながら、ドームや大型船の骨組みのような構造をイメージしながら描いていたそのかたちは、後にコラボレーション作品を展開することになったある現代詩の詩人によって、廃墟を連想させる、いや廃墟そのものだ、と指摘され、気付かされ、自分の中で廃墟なのだと認識した。
具体的なイメージのよりどころがあるというのはありがたいもので、その後しばらくは廃墟をキーワードに制作を続けた。自分が創り出したいと思っていたものに、自分の外から名称なりカテゴリーなりを割振られる事には、深層意識での小さな拒絶感を伴いながらも、何か気の休まるような落着く感覚があるものだ。未知なる物を抱える不安に対して、安心感と制度的な認知が得られたような気にさせられる。

やがて、それこそ廃墟をモチーフに映像を撮りつづけている映画作家と、先の私と廃墟を結び付けてくれた詩人とで、コラボレーションワークのシリーズを展開することになる。
それは、私にとってもメンバーである彼らにとっても、最高に刺激的なものであった。そんな中で、「自分のコンセプトは画面に廃墟を新築する行為にある」と言い切っていたこともあるのだが、その後の廃墟ブームの影響もあってか、廃墟という言葉にしっくりとこないものを感じ始めた。というより、最初からあった小さな違和感・拒絶感が表に出始めたのだろう。
もともと廃墟に纏わりつく人間生活の痕跡や歴史的背景などにはほとんど興味がなく、また、最初に自分の作品がそう見られたときの新鮮さも感動もなく、単に説明しやすい便利な言葉として、ニュアンスの違いには眼をつぶって多用しすぎた反省もあった。今から思えば、「解体されつつある廃工場的な無機能構造物に対する憧憬に基いた、日常空間とのズレを表出させる試み」とでも言っておくべきだったか。それもまどろっこしい。わかったようなわからないような。
あそこに立った時のあの感覚。それが一番しっくりくる。
じつは、私にとって廃工場に感じる想いと同質なものを呼び起こすものがある。
それはクラシックカメラ、あるいは機械式の中古・ジャンク(壊れた)カメラである。
メカニカルで機能的で、どこか無理やりだったり大げさだったり見事だったりする機械的な連動、意外に単純で美しいシステム構造、ひたすら性能と生産性を求めた人類の叡智と職人の技の結晶。それを分解・解体しては、時に修理に専念し、時に解体しっ放しで眺めている。
というわけで、廃工場を探すでもなく、出会うでもなく、それでもその空間(と同質なもの)に浸りたいときには、中古カメラ屋に行く。馴染みの店主と話をしながら、1〜2時間ほどあれやこれやを見せてもらいながら、いじる。で、ほぼ必ず何かしら買ってしまう。それがささやかなストレス解消手段にもなっている。こちらは工場と違って思いたったらでかけていけるという手軽さと、自分のものとして手のひらに保有することが出来ていつでも味わえるという利点がある。
お手軽だということは、あまり良いコトではない。そう思いながらも、ストレスの数の壊れたカメラに囲まれながら、小さな「私の空間」に浸っている。
<「嵯峨芸術」2008原稿より>
08/06/16
表現の原点・・・
ほんの小さな子供でも、鉛筆を持たせてみると、壁や床に向かって夢中で線を描き続けます。その、行為や痕跡を楽しむ姿を見ていると、「描く」ということも人間の本能としてもともと備わったものではないのかと驚かされます。
確かに私たちの意識の中には、いろいろな約束事にとらわれずに線を引きまくったり、色を塗りまくったりしたい衝動が常にどこかにあります。
私達はその本能的な行為を芸術表現として行っていこうとしているわけです。
そこには、本能の理性的な開放に加えて、新しさと普遍性をもった造形言語による説得力が必要となります。それらの総合的な力量が、感性であり、観察力であり、表現力と呼ばれるものなのではないかと思います。
そして、描くことによってのみ立ち現れるリアリティーを求めていくことが絵画の楽しさであると思います。
そのような絵画の世界を皆さんと一緒に探求していきたいと思います。
<2002 大学案内>
07/05/19
確かに私たちの意識の中には、いろいろな約束事にとらわれずに線を引きまくったり、色を塗りまくったりしたい衝動が常にどこかにあります。
私達はその本能的な行為を芸術表現として行っていこうとしているわけです。
そこには、本能の理性的な開放に加えて、新しさと普遍性をもった造形言語による説得力が必要となります。それらの総合的な力量が、感性であり、観察力であり、表現力と呼ばれるものなのではないかと思います。
そして、描くことによってのみ立ち現れるリアリティーを求めていくことが絵画の楽しさであると思います。
そのような絵画の世界を皆さんと一緒に探求していきたいと思います。
<2002 大学案内>
07/05/19
表現の原点!?
まだ小さい子供の、カタコトでの身振り手振りを交えた言葉に、はっと核心を衝かれた思いをすることがあります。
少ないボキャブラリーで知っている限りの単語を駆使して、また時には新しい言葉(の様なもの)を創ってまで伝えようとする様子には、驚くほど感動的で、強い、詩的な言葉(もの)があります。
そこには「表現」のもつ、大きな力の原点が潜んでいるように思います。
ここ(京都嵯峨芸術大学)での4年間を、油絵の具で絵を描くことをベースに置きながら、何を、どのように見つめ、何が見つけられるのか、何を伝えたいのか、そのために何をするべきなのか、をじっくりと考えながら過ごす、厳しくも楽しい場にしてもらいたいと思います。
<2004 大学案内>
07/05/19
少ないボキャブラリーで知っている限りの単語を駆使して、また時には新しい言葉(の様なもの)を創ってまで伝えようとする様子には、驚くほど感動的で、強い、詩的な言葉(もの)があります。
そこには「表現」のもつ、大きな力の原点が潜んでいるように思います。
ここ(京都嵯峨芸術大学)での4年間を、油絵の具で絵を描くことをベースに置きながら、何を、どのように見つめ、何が見つけられるのか、何を伝えたいのか、そのために何をするべきなのか、をじっくりと考えながら過ごす、厳しくも楽しい場にしてもらいたいと思います。
<2004 大学案内>
07/05/19
受験生の頃
受験生のとき。どうしても思うように石膏デッサンが上手く描けない。先生の「君はちゃんとに見えてみてない。」のひとことに、「そうだ!きっとめがねの度があわなくなってきているに違いない。そういえば遠くの細かい字もぼやけるような・・・。」と、目からうろこが落ちた思いで、その日のうちに恐ろしく度のキツイめがねを小遣いはたいて新調した。
キツ過ぎるそのめがねは目が回ってしまうので日常生活には不自由だったけど、いざデッサンをするぞという時には、石膏像の隙間の細かいチリや傷まで克明に見える!!
デッサン用秘密兵器として(なぜか)温存し、入試本番で満を持して使った。・・・のだが、当然のように悲惨な結果に終わった。・・・真剣だったのに。
「観る」ことと「見えてる」ことの違いがわかったのはずっと後のこと。絵を描くにはもうひとつの眼が開かなきゃいけないんだとわかった。
そのときのめがねは今も引き出しの隅にあるのだけど、かけると今でも目が回る。
07/05/19
キツ過ぎるそのめがねは目が回ってしまうので日常生活には不自由だったけど、いざデッサンをするぞという時には、石膏像の隙間の細かいチリや傷まで克明に見える!!
デッサン用秘密兵器として(なぜか)温存し、入試本番で満を持して使った。・・・のだが、当然のように悲惨な結果に終わった。・・・真剣だったのに。
「観る」ことと「見えてる」ことの違いがわかったのはずっと後のこと。絵を描くにはもうひとつの眼が開かなきゃいけないんだとわかった。
そのときのめがねは今も引き出しの隅にあるのだけど、かけると今でも目が回る。
07/05/19
|→