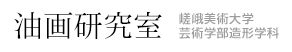嵯峨美術大学・油画研究室オフィシャルサイト|TOP|
卒業作品制作レポート
「卒業制作について」 田中 里実
「卒業制作について」 田中 里実

「レポート要旨」
共感覚の世界はまだまだ発展途上で、一概に言えない点が多くある。しかし脳の働きから通様相知覚の極端が共感覚だということになると、万人に本能的に、深いところで
脳に直接刺激を与えられるものが創れるのではないだろうか。また、自身の「描く」という姿勢は、描きたい欲求と描かされる状態を把握したのちに確立されていくものであり、原始的な捉え方だけではそう長くは続かない。
そして京都という地域は日本人の感性がもっとも強調され、賞賛された場所である。日本人のもつ感性の豊かさは様々な面で「美」を感じさせ、さらに育ててくれたが、いつしか日本人は感性しか豊かでなくなってしまった。感性の豊かさで言えば諸外国の中でも群を抜くほどのものではあるのだが、それに伴う知性をいつしか脱ぎ捨てた。今、日本人には知性を育てることが欲求されているのではないだろうか。
序論
4年間の絵画作品を経て見出したテーマ「共感覚」について、共感覚者であるわたしの体験を基に、この先の絵画あるいは美術の世界でどのような展開が望めるのかを考察する。また、自身の「描く」行為に対しての現時点での考えを発表するとともに、さらに出てきた疑問を問いかける。
そして、京都に立地する大学に4年間通うことで何が恵まれ何を隠されてきたのか、振り返って得たものをもとに、更に必要な要素は何なのかを考える。
「音をみるということ」
自身の制作においてここしばらくは音を描いてきている。3回生の頃、「ファ」ってオレンジ色で横伸びの広がり方をするからそれを一度描いてみよう、ということで描きだしたのがきっかけであった。それから一年以上経ったある日、「共感覚」という言葉に出会った。共感覚(共感覚知覚あるいは共伴感覚)とは別々の感覚が同時に発現することである。わたしの場合は聴覚と視覚であった。更に細かく分ければ、視覚でも数字から色を感じる、文字を感じるなどがあるが、わたしの場合は音(環境音の中で目立った音・あるいは旋律)から色をみる。また色だけでなく形や線をみることもある。物心が付きいつの間にか見えていて、みんな見えているものだと思っていたので大して疑問には思っていなかったが、小学生のある日そのことを言うとからかわれ、それから自分はおかしいんだと思い公言しなくなった。
これは共感覚者によくみられることである。共感覚の研究はここ2〜30年ほどしかされていない。共感覚の記述は約200年前に医学的にされているのだが、それは想像上のものだとされてきた。ところが21世紀に入った頃、実在の現象であると医学的に認められ検証がされ始めたのだ。わたしのようにおかしな人だと思われるのを恐れ、周囲に言わずに生活してきた人が多いのもこの研究が遅れた一つの要因だろう。
通様相知覚という言葉を知っているだろうか。これは異なる感覚系の間で相互影響が与えられるということである。「黄色い声援」「渋い色」など視覚と聴覚、味覚と視覚といった異なる感覚系で共通するものがあることがある。また日本の三大芸道「茶道」「華道」「香道」の香道も御香の薫りを聴くというのもその1つであろう。共感覚はこれらの通様相知覚が極端になっているものなのである。共感覚者の中には食べ物を食べるとその味覚に沿った形を腕や手の内にはっきりと感じ取ることができる人もいる。
これらのことから共感覚はただ珍しいものではなく、その元を辿る過程で、万人に共通しているということが見受けられる。このことが絵画、あるいは美術の分野に対して有効であるポイントとなるのではないかとわたしは考えている。
わたしの場合は音を聴いて色が見えるという現象だが、最初に述べたようにファの音がオレンジ色だと言うのは、共感覚者に共通しているものではない。それぞれに見える色があり、その対(ファはオレンジなど)はぶれることがないのである。しかし、同じ音に対して抱く色が違えど、それはその人の色彩感覚やもっている幅の違いだけであって、全体をみれば同じような捉え方をしているのだと考えている。気温が10度の土地で北海道の人が何とも思わなくとも沖縄の人が寒いと感じるのと似ているように、10度という1つの要素に対して持っている感覚、皮膚の慣れが違うだけであるということだ。
共感覚の要素を作品に取り込むことで、観る側の人間は目だけでなく脳で観ることも可能になるのではないだろうか。もちろん、目でみることも脳に刺激が送られるものではあるのだが、共感覚の要素を使う事によってより直接的に・直感的に脳に印象を与えられるのではないかと考えている。そこで、絵画作品から音や味を感じることができれば視覚芸術と言われてきた美術の世界がもっと興味深いものになるはずだ。これには科学との、特に脳科学との提携が重要になってくる。今は共感覚の研究として脳科学者が数名研究を始めているが、まだ研究途中でなかなか本をみてもバラバラな報告である。それほどまだ浅いジャンルであるからこそ、共感覚者たちが公言し、研究対象となっていかなければならない。その方法としてわたしは美術、絵画を提出したい。しかしわたしにとってそれはただの過程であり、共感覚自体も手法のひとつにすぎない。共感覚を『駆使』することが作品として成り立つには必要になってくる。
「描きたいけど描かされる、けど描く」
わたしにとって描くこととは何なんだろうか、という素朴で重大な疑問は今でも持ち続けている。上文で述べたように、音を聴くと色がみえるということから、その色や形などはわたしの脳が生み出したものであっても、それはわたしの意図するところではない。ファを聴けばオレンジ色が出てきてしまうのだ。柿の皮のような色が。
絵画と音楽には大きく時間軸の違いがある。この音を描こう、このメロディーの部分を描こうとしていても、色や形は次々に出てきては消えていく。それに対して人の手で描くことが間に合うかと考えれば到底難しいことはわかっているはずである。それに追いつけず、悔しくなり追いつこうと努力する。必死になる。するとそれはもはや描かされている状態に近いのである。音に描かされている状態は、音を描いているとは呼べない。自分のペースを保つため、作品として創るために、わたし自身がコントロールされるのではなく、コントロールする要素を取り入れなければならない。それから意識して人を描いている。顔が多いのは顔が最も描き応えがあるからだ。自分の感性のみで描ける領域を確保できたことで、作品として完成させる意識はもちろん、共感覚の要素をただ描くのではなく、どのように取り入れていくのかを考えることができるようになる。
音という時間軸を要するものを表現するのに、なぜ絵画なのか。なぜ映像などで表現しないのか。それは絵画だからこそ描くんだということである。率直に言えば、絵画で勝負したいのである。絵画で時間軸を表現することは可能なのではないか。それには技術も必要であろう。体得しなければならない何かもたくさんあるはずである。絵画であるからこそ、時間軸に対して意識が持てるのだ。
卒業制作を制作するにあたって、いつもなら綿布をパネル張りし、下地等をおいてから油彩での表現だったのを、綿布を染色したものをパネル張りするということをした。これには音を表現するうえで「響き」「浸透」を油彩で表現するよりも、染色で表現する方がわたしの中から出てきたその色や形の“質”に近いのだ。音は粒であり、その細かさ、硬さ、数、空気中への広がり方などが全く異なってくる。染色での表現は反応染料を用いて、すべて10号ほどの筆で描いている。型染めやロウケツなどの方が効率よくできるのでは、という声をよく聞いたが、あくまでも「絵画」として制作しているため、やはり自分の手で描きたかった。これもある種「コントロールしたい」という思いが入っているのだろう。
描くことは「描かされる」ことと「描きたい」ことに大きく分かれているのではないか。きっとどちらか一方が強い状態ではいけない。描いている最中の自分の状態を把握すること、自分の欲求を整理すること、これだけ見れば冷たく何とも熱のない制作姿勢に見えるかも知れないが、描く行為に対して原始的な捉え方ばかりではそう長く続かないのではないか。どこかで理論的に、合理的にものを考える人間としては、少なからずその過程を経て描いているのだと考えている。
「京都」
京都に立地しているこの大学は大阪の家から一時間と少しで行ける。電車の時間だけで見ると大阪に出るよりも京都に出る方が近い。そのため知らずのうちに生活に「京都」が流れ込んでいたため、この大学に通っていても大きく差を感じることは少なかった。ところが、京都以外の芸術大学に少しずつ行くようになってから、京都はとても特殊だということがわかった。言葉遣いに、食事やその様式に、生活のあらゆる面で「美しさ」を意識していることがわかってきた。これは日本人に強い傾向であり、特に京都はそれが洗練されている地域でもある。
日本人のこの感性豊かな面は素晴らしいことなのであろうが、それ自体を判断や基準の中心に持っていこうとする点は、諸外国から発展の遅れをとってしまう要因になり兼ねないような気がする。
わたし自身が感覚で描いてきた点が多く、「言葉にできないから描いているんだ」と豪語していたが、やはり描き手としては言葉も使っていかなければならないのである。そのためには知性が必要になってくる。これは日本が諸外国からすでに遅れをとっている点だ。感性で許されることが多い日本は武器としての知識や語彙をそっと傍らに置いてきてしまった。
今や日本では感性の豊かさを育てることが目的よりも、知性を育てることが重要なのではないかとわたしは考えている。感性の豊かさはすでに日本人の武器なのだ。特にこの京都という洗練された地域の芸術大学に通っている人たちは、感性や感覚がより強く許されるこの地域に対してどのような温度を感じているのだろう。京都は制作がしやすい環境だということはよく耳にする。確かに自然や分野で恵まれた環境がそろっているのは確かである。だからこそ、それに温かい温度だけを感じているようではいけないのだ。感性を育てることは難しい。だから日本人はとても恵まれた感性の持ち主である。知性の豊かさを身につけるにも多くの時間を要するが、わたしが思うに、感性を育てるよりも知性を育てる方がはるかに簡単なのではないかと考えている。いわゆる、武器としての言葉を身につければいいのだ。「言葉にできないから描く」というのは日本人にとって好都合な言い訳だったのかも知れない。わたしが日本人であるからこそ、この疑問をみなさんに問いかけたい。知性の無さを怖いと感じたことはないだろうか。
「まとめ」
卒業制作に取り掛かる前に「共感覚」という言葉に出会い、自分がそれに当てはまることから慌てるように調べだした。もしその言葉に出会っていなかったら、「ファはオレンジでこんな形で云々〜。」と見える世界をつらつら書いていただろう。まだ研究が進んでいないことから、一概に言えない点は多いが、脳で何かが起こっていることには間違いない。美術と科学は密接な関係であることを今回身をもって感じた。
また染色の技法研究も大きな経験値となっている。音を表現するうえで油彩に固着していたわたしを違う場所へ連れて行ってくれたようなものだ。しかし、ここでわたしにとっての今後の課題が見える。
確かに染色で表現するには音の「響き」や「浸透」、「透明感」などは表現しやすい。しかし絵画と呼べるには、染料を筆で描きました、と言うよりも油絵具でその響きや透明感を表現している方がペインタリーな空気は漂う。そこが問題なのだ。油絵具で透明感を追求したならば、それはそれで問題であり、透明感は油彩ではなく染色の方が得意分野なのであるから、全部を染色にすればいいじゃないか、ということになる。かと言ってすべて染色でしたものだとそれは絵画ではなく染色作品と取られる。わたしは絵画でやっていきたいと考えているだけあり、卒業制作も染色を絵画技法の1つとして取り入れたまでである。しかし、1つの画面に染色と油彩を混在させるのは難しいことであり、下手をすれば互いを殺しあう要素ともなる。
この「染色」の存在の強みを今後もっと見出せたら、わたしの「絵画」の要素としての取り入れ方が変わってくるであろうし、また絵画を選択し、絵画をやっていくということへの強みにも変換されるだろう。様々なメディアの中でも「絵画です」と言い切れるまでに至るには、この課題を乗り切ることがまず必要であろう。
参考文献
共感覚―もっとも奇妙な知覚世界 ジョン・ハリソン著 松尾香弥子訳/新曜社/2006
共感覚者の驚くべき日常―形を味わう人、色を聴く人 リチャード・E・シトーウィック著 山下篤子訳/草思社/2002
音に色が見える世界 岩崎純一著/PHP研究所/2009
10/06/15

「レポート要旨」
共感覚の世界はまだまだ発展途上で、一概に言えない点が多くある。しかし脳の働きから通様相知覚の極端が共感覚だということになると、万人に本能的に、深いところで
脳に直接刺激を与えられるものが創れるのではないだろうか。また、自身の「描く」という姿勢は、描きたい欲求と描かされる状態を把握したのちに確立されていくものであり、原始的な捉え方だけではそう長くは続かない。
そして京都という地域は日本人の感性がもっとも強調され、賞賛された場所である。日本人のもつ感性の豊かさは様々な面で「美」を感じさせ、さらに育ててくれたが、いつしか日本人は感性しか豊かでなくなってしまった。感性の豊かさで言えば諸外国の中でも群を抜くほどのものではあるのだが、それに伴う知性をいつしか脱ぎ捨てた。今、日本人には知性を育てることが欲求されているのではないだろうか。
序論
4年間の絵画作品を経て見出したテーマ「共感覚」について、共感覚者であるわたしの体験を基に、この先の絵画あるいは美術の世界でどのような展開が望めるのかを考察する。また、自身の「描く」行為に対しての現時点での考えを発表するとともに、さらに出てきた疑問を問いかける。
そして、京都に立地する大学に4年間通うことで何が恵まれ何を隠されてきたのか、振り返って得たものをもとに、更に必要な要素は何なのかを考える。
「音をみるということ」
自身の制作においてここしばらくは音を描いてきている。3回生の頃、「ファ」ってオレンジ色で横伸びの広がり方をするからそれを一度描いてみよう、ということで描きだしたのがきっかけであった。それから一年以上経ったある日、「共感覚」という言葉に出会った。共感覚(共感覚知覚あるいは共伴感覚)とは別々の感覚が同時に発現することである。わたしの場合は聴覚と視覚であった。更に細かく分ければ、視覚でも数字から色を感じる、文字を感じるなどがあるが、わたしの場合は音(環境音の中で目立った音・あるいは旋律)から色をみる。また色だけでなく形や線をみることもある。物心が付きいつの間にか見えていて、みんな見えているものだと思っていたので大して疑問には思っていなかったが、小学生のある日そのことを言うとからかわれ、それから自分はおかしいんだと思い公言しなくなった。
これは共感覚者によくみられることである。共感覚の研究はここ2〜30年ほどしかされていない。共感覚の記述は約200年前に医学的にされているのだが、それは想像上のものだとされてきた。ところが21世紀に入った頃、実在の現象であると医学的に認められ検証がされ始めたのだ。わたしのようにおかしな人だと思われるのを恐れ、周囲に言わずに生活してきた人が多いのもこの研究が遅れた一つの要因だろう。
通様相知覚という言葉を知っているだろうか。これは異なる感覚系の間で相互影響が与えられるということである。「黄色い声援」「渋い色」など視覚と聴覚、味覚と視覚といった異なる感覚系で共通するものがあることがある。また日本の三大芸道「茶道」「華道」「香道」の香道も御香の薫りを聴くというのもその1つであろう。共感覚はこれらの通様相知覚が極端になっているものなのである。共感覚者の中には食べ物を食べるとその味覚に沿った形を腕や手の内にはっきりと感じ取ることができる人もいる。
これらのことから共感覚はただ珍しいものではなく、その元を辿る過程で、万人に共通しているということが見受けられる。このことが絵画、あるいは美術の分野に対して有効であるポイントとなるのではないかとわたしは考えている。
わたしの場合は音を聴いて色が見えるという現象だが、最初に述べたようにファの音がオレンジ色だと言うのは、共感覚者に共通しているものではない。それぞれに見える色があり、その対(ファはオレンジなど)はぶれることがないのである。しかし、同じ音に対して抱く色が違えど、それはその人の色彩感覚やもっている幅の違いだけであって、全体をみれば同じような捉え方をしているのだと考えている。気温が10度の土地で北海道の人が何とも思わなくとも沖縄の人が寒いと感じるのと似ているように、10度という1つの要素に対して持っている感覚、皮膚の慣れが違うだけであるということだ。
共感覚の要素を作品に取り込むことで、観る側の人間は目だけでなく脳で観ることも可能になるのではないだろうか。もちろん、目でみることも脳に刺激が送られるものではあるのだが、共感覚の要素を使う事によってより直接的に・直感的に脳に印象を与えられるのではないかと考えている。そこで、絵画作品から音や味を感じることができれば視覚芸術と言われてきた美術の世界がもっと興味深いものになるはずだ。これには科学との、特に脳科学との提携が重要になってくる。今は共感覚の研究として脳科学者が数名研究を始めているが、まだ研究途中でなかなか本をみてもバラバラな報告である。それほどまだ浅いジャンルであるからこそ、共感覚者たちが公言し、研究対象となっていかなければならない。その方法としてわたしは美術、絵画を提出したい。しかしわたしにとってそれはただの過程であり、共感覚自体も手法のひとつにすぎない。共感覚を『駆使』することが作品として成り立つには必要になってくる。
「描きたいけど描かされる、けど描く」
わたしにとって描くこととは何なんだろうか、という素朴で重大な疑問は今でも持ち続けている。上文で述べたように、音を聴くと色がみえるということから、その色や形などはわたしの脳が生み出したものであっても、それはわたしの意図するところではない。ファを聴けばオレンジ色が出てきてしまうのだ。柿の皮のような色が。
絵画と音楽には大きく時間軸の違いがある。この音を描こう、このメロディーの部分を描こうとしていても、色や形は次々に出てきては消えていく。それに対して人の手で描くことが間に合うかと考えれば到底難しいことはわかっているはずである。それに追いつけず、悔しくなり追いつこうと努力する。必死になる。するとそれはもはや描かされている状態に近いのである。音に描かされている状態は、音を描いているとは呼べない。自分のペースを保つため、作品として創るために、わたし自身がコントロールされるのではなく、コントロールする要素を取り入れなければならない。それから意識して人を描いている。顔が多いのは顔が最も描き応えがあるからだ。自分の感性のみで描ける領域を確保できたことで、作品として完成させる意識はもちろん、共感覚の要素をただ描くのではなく、どのように取り入れていくのかを考えることができるようになる。
音という時間軸を要するものを表現するのに、なぜ絵画なのか。なぜ映像などで表現しないのか。それは絵画だからこそ描くんだということである。率直に言えば、絵画で勝負したいのである。絵画で時間軸を表現することは可能なのではないか。それには技術も必要であろう。体得しなければならない何かもたくさんあるはずである。絵画であるからこそ、時間軸に対して意識が持てるのだ。
卒業制作を制作するにあたって、いつもなら綿布をパネル張りし、下地等をおいてから油彩での表現だったのを、綿布を染色したものをパネル張りするということをした。これには音を表現するうえで「響き」「浸透」を油彩で表現するよりも、染色で表現する方がわたしの中から出てきたその色や形の“質”に近いのだ。音は粒であり、その細かさ、硬さ、数、空気中への広がり方などが全く異なってくる。染色での表現は反応染料を用いて、すべて10号ほどの筆で描いている。型染めやロウケツなどの方が効率よくできるのでは、という声をよく聞いたが、あくまでも「絵画」として制作しているため、やはり自分の手で描きたかった。これもある種「コントロールしたい」という思いが入っているのだろう。
描くことは「描かされる」ことと「描きたい」ことに大きく分かれているのではないか。きっとどちらか一方が強い状態ではいけない。描いている最中の自分の状態を把握すること、自分の欲求を整理すること、これだけ見れば冷たく何とも熱のない制作姿勢に見えるかも知れないが、描く行為に対して原始的な捉え方ばかりではそう長く続かないのではないか。どこかで理論的に、合理的にものを考える人間としては、少なからずその過程を経て描いているのだと考えている。
「京都」
京都に立地しているこの大学は大阪の家から一時間と少しで行ける。電車の時間だけで見ると大阪に出るよりも京都に出る方が近い。そのため知らずのうちに生活に「京都」が流れ込んでいたため、この大学に通っていても大きく差を感じることは少なかった。ところが、京都以外の芸術大学に少しずつ行くようになってから、京都はとても特殊だということがわかった。言葉遣いに、食事やその様式に、生活のあらゆる面で「美しさ」を意識していることがわかってきた。これは日本人に強い傾向であり、特に京都はそれが洗練されている地域でもある。
日本人のこの感性豊かな面は素晴らしいことなのであろうが、それ自体を判断や基準の中心に持っていこうとする点は、諸外国から発展の遅れをとってしまう要因になり兼ねないような気がする。
わたし自身が感覚で描いてきた点が多く、「言葉にできないから描いているんだ」と豪語していたが、やはり描き手としては言葉も使っていかなければならないのである。そのためには知性が必要になってくる。これは日本が諸外国からすでに遅れをとっている点だ。感性で許されることが多い日本は武器としての知識や語彙をそっと傍らに置いてきてしまった。
今や日本では感性の豊かさを育てることが目的よりも、知性を育てることが重要なのではないかとわたしは考えている。感性の豊かさはすでに日本人の武器なのだ。特にこの京都という洗練された地域の芸術大学に通っている人たちは、感性や感覚がより強く許されるこの地域に対してどのような温度を感じているのだろう。京都は制作がしやすい環境だということはよく耳にする。確かに自然や分野で恵まれた環境がそろっているのは確かである。だからこそ、それに温かい温度だけを感じているようではいけないのだ。感性を育てることは難しい。だから日本人はとても恵まれた感性の持ち主である。知性の豊かさを身につけるにも多くの時間を要するが、わたしが思うに、感性を育てるよりも知性を育てる方がはるかに簡単なのではないかと考えている。いわゆる、武器としての言葉を身につければいいのだ。「言葉にできないから描く」というのは日本人にとって好都合な言い訳だったのかも知れない。わたしが日本人であるからこそ、この疑問をみなさんに問いかけたい。知性の無さを怖いと感じたことはないだろうか。
「まとめ」
卒業制作に取り掛かる前に「共感覚」という言葉に出会い、自分がそれに当てはまることから慌てるように調べだした。もしその言葉に出会っていなかったら、「ファはオレンジでこんな形で云々〜。」と見える世界をつらつら書いていただろう。まだ研究が進んでいないことから、一概に言えない点は多いが、脳で何かが起こっていることには間違いない。美術と科学は密接な関係であることを今回身をもって感じた。
また染色の技法研究も大きな経験値となっている。音を表現するうえで油彩に固着していたわたしを違う場所へ連れて行ってくれたようなものだ。しかし、ここでわたしにとっての今後の課題が見える。
確かに染色で表現するには音の「響き」や「浸透」、「透明感」などは表現しやすい。しかし絵画と呼べるには、染料を筆で描きました、と言うよりも油絵具でその響きや透明感を表現している方がペインタリーな空気は漂う。そこが問題なのだ。油絵具で透明感を追求したならば、それはそれで問題であり、透明感は油彩ではなく染色の方が得意分野なのであるから、全部を染色にすればいいじゃないか、ということになる。かと言ってすべて染色でしたものだとそれは絵画ではなく染色作品と取られる。わたしは絵画でやっていきたいと考えているだけあり、卒業制作も染色を絵画技法の1つとして取り入れたまでである。しかし、1つの画面に染色と油彩を混在させるのは難しいことであり、下手をすれば互いを殺しあう要素ともなる。
この「染色」の存在の強みを今後もっと見出せたら、わたしの「絵画」の要素としての取り入れ方が変わってくるであろうし、また絵画を選択し、絵画をやっていくということへの強みにも変換されるだろう。様々なメディアの中でも「絵画です」と言い切れるまでに至るには、この課題を乗り切ることがまず必要であろう。
参考文献
共感覚―もっとも奇妙な知覚世界 ジョン・ハリソン著 松尾香弥子訳/新曜社/2006
共感覚者の驚くべき日常―形を味わう人、色を聴く人 リチャード・E・シトーウィック著 山下篤子訳/草思社/2002
音に色が見える世界 岩崎純一著/PHP研究所/2009
10/06/15

旧・京都嵯峨芸術大学 油画分野(オフィシャルサイト)